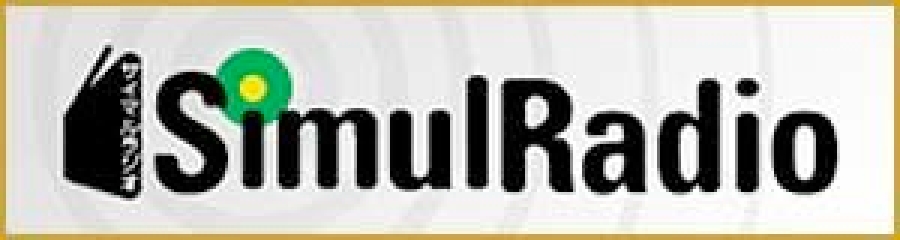八重山の諺に「粗(あら)さーどぅ美(かい)しゃ」と言う諺がある。
直訳すれば「荒削りこそ美しい」、技巧をこらさない素朴なのがのが美しい、
と言うのである。
平たく言えば未完の美、シンプルイズベストなのである。
〈かいしゃ〉は「月ぬ美しゃ」などの唄で知られている語幹で「美しい」
(光、形など)を意味します。
大和には「彫琢朴に還る」(ちょうたくぼくにかえる)類似語がある。
苦労して技巧を凝らして何かを仕上げるが、最終的には飾り気のない素朴な状態に戻る。という意味。
偉大な人物の在り方や、素朴本来の味を生かす考え方などを表す言葉として逆説的に使われます。
高度な技術や労力を尽くして、物事を完璧に仕上げる、しかし、その最終形は、
最初から飾り気がなく、素朴で自然なありのままの姿、あるいは本来の素朴の美しさを際立たせた状態である。
その際立たせた状態を八重山では「粗さーどぅ美しゃ」と言うのである。
皆さんも良くご存知の
八重山の抒情唄「とぅばらーま」の歌詞にも「月ぬ美しゃ 十三夜月 美童美しゃ十七・八頃」と
歌うのも満月よりも十三月が輝いて美しい、乙女は十七歳・十八歳ころが美しいと。
と歌うところから「とぅばらーま大会」は満月の十五夜ではなしに毎年中秋の13夜月に昭和22年から
開催されるようになりました。(因みに今年は10月4日開催されます)
昨日の「U-18島歌者コンテスト」で歌う若者達の唄を審査しながら聞いていて
飾らないで素朴に歌う一人一人若者の唄が輝き愛おしくもあり改めて「粗さーどぅ美しゃ」
愚生の好きな諺が深く心に響きました。
![]()